|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
おじいちゃんはとにかくお相撲が大好きだ。子供の頃は村で一番強くて、さらには隣の村の大会まで出ていって優勝を果たし、賞をたくさんとったそうだ。おかげでノートや鉛筆などの文房具は買わなくてすんでいたらしい。
ぼくもお相撲は大好きだ。それはおじいちゃんが蔵前国技館に連れて行って、生のお相撲を観させてくれるから。鍛えあげられた男同士の勝負、ぼくは本当にすごいと思う。
おじいちゃんは特に『佐渡ヶ嶽部屋』というお相撲部屋を応援していて、よくぼくはおじいちゃんに、朝稽古の見学に連れて行ってもらう。150キロ以上もあるお相撲さんたちの稽古は本当にすごい迫力だ。特に『琴櫻』は猛牛のような突進力で、ものすごい迫力と強さで相手をぶちかまし、押し出す。稽古が終わるとお相撲さんたちといっしょにちゃんこを食べるのだけれど、これが本当に美味しい。おじいちゃんはこの部屋のお相撲さんたちのことをみんな知っていて、四股名を全部覚えているのはすごいとつくづく思う。
おうちに帰ってきてから、おじいちゃんがぼくにいった。「さっきの朝稽古の話だけれど、特にあの『琴櫻』はすごいだろう!いずれ必ず横綱になるお相撲さんだよ。」ぼくもいった。「本当にすごかったね!ぼくもこれから『琴櫻さん』を応援するよ!」おじいちゃんはにっこりと笑ってとても嬉しそうな顔をした。その後、しばらくして『琴櫻さん』は本当に横綱になった。おじいちゃんとぼくは手と手を取り合って心の底から喜んだ。
お相撲といえばこんなことがあった。おじいちゃんのお弟子さんたちが集まっての忘年会がぼくのおうちであったときのこと、みんなお酒を飲んで酔っぱらってきた頃に、一人の若い先生がおじいちゃんにこういった。「大先生、今日は私と相撲で勝負してもらえないでしょうか?」周りの先生たちも一瞬静かになった。おじいちゃんはいつもと変わらず笑いながら「よっしゃー!やろう!」と席を立った。
みんなが食事しているテーブルをつないだ輪の中に、二人で入って向かい合った。ぼくはとても心配だったけれど「おじいちゃん!頑張れー!」と声援を送った。おじいちゃんは腕まくりをして真剣な顔になった。「はっけよーい!のこった。」の声がした瞬間、若い先生は猛烈におじいちゃんにぶつかっていった。しかし60歳を過ぎているおじいちゃんは平気な顔をして分厚い胸板で相手のぶちかましを受け止めた。二人は四つ相撲でしばらくこう着状態になった。おじいちゃんの額からは一つ二つ汗が流れている。相手の20歳代の先生も一生懸命におじいちゃんのベルトをまわしのごとくつかんでいる。ぼくは長引けば長引くほどおじいちゃんが不利になると思い、テーブルを乗り越えて相手の左足にタックルした。そして足を持ち上げた瞬間、おじいちゃんの上手投げが見事に決まった。
周りの先生たちはいっせいにぼくに声援を送ってくれた。「ター坊、よくやったぞー!」「さすが、三代目ナイスタックル」「よくおじいちゃんを守ったー!えらいぞー!」ぼくはちょっとばかり卑怯だと思ったけれど、おじいちゃんやみんなが本当に盛り上がっていることにとても満足した。
すると、おじいちゃんとお相撲をとっていた若い先生がぼくのところに来て「さすがター坊だな!みごとに一本とられたよ。」といって握手をしてくれた。パパもママもタックのおばちゃんもみんなぼくを見て笑っている。おじいちゃんは「とんだ飛び入りのおかげで勝つことができたけど、この勝ちはター坊に譲るとしよう!」というと、いつも以上に大きな声で「わっはっはー!」と笑った。
いつもはおじいちゃんに助けられてばかりだけれど、この日はぼくが初めておじいちゃんを助けたような気持ちになった日だった。
|
| 先代佐渡ヶ嶽親方(第53代横綱琴櫻)本名鎌谷紀雄氏が平成19年8月14日にお亡くなりになられました。祖父徳治郎、父徹、私孝と浪越家親子三代に渡り、先代佐渡ヶ嶽親方には大変お世話になりました。心からの御冥福をお祈りいたします。 |
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
いつもおじいちゃんの周りには、いろいろな人がたくさん集まってくる。お友達やお仕事の関係の人。お仕事の関係でも同じお仕事をしている人と、まったくちがうお仕事をしている人。ぼくは、おじいちゃんと伝通院さんでおばあちゃんのお墓にお水をあげながら、いつも疑問に思っていることを聞いてみた。
「おじいちゃんの周りには、いつもたくさんの人がいるけれど、みんな、おじいちゃんとはお友達なの?」おじいちゃんは突然のぼくの質問にこう答えた。「なるほど、ター坊、それは面白い質問だな。おじいちゃんが思うには、同じ仕事をしている人とのお付き合いも大事だけれど、もっと大事なのは、自分の仕事とはちがういろいろなお仕事をしている人とのお付き合いの方なんだよ!」
ぼくは、おじいちゃんにたずねた。「何でおんなじお仕事の人よりも、ちがうお仕事をしているお友達のほうが大切なの?」すると、おじいちゃんは答えた。「自分とはちがういろいろなお仕事をしている人たちからは、自分の知らないことを教えてもらったり、ちがう苦労や楽しみを聞くことができるからさ!だからおじいちゃんにとって、そういう人たちはみんなお友達なんだよ。そして見聞を広めることがとても大切なんだよ。」
ぼくは、おじいちゃんにさらに聞いた。「それじゃ、おんなじお仕事をしている人はお友達じゃないの?」おじいちゃんは静かに笑いながら答えた。「みんな、お友達じゃ困るだろう!仕事場というのは遊ぶところじゃないんだから。だから仕事をいっしょにしている人たちと、自分の友達とは一線を引かなくてはいけないものなんだよ。」
ぼくは、さすがおじいちゃんだと思った。「だからおじいちゃんは、遊びに行ったり、食事をしたり、お酒を飲むのもお友達とするんだね!」「おー、そうだとも。ター坊も大人になったら、いろいろなお仕事をしている人たちを友達に持つんだよ。そして素晴らしい人間関係の中から、人間としての器を大きくするんだよ!」ぼくは、そう教えてくれたおじいちゃんの心も人間もとっても大きく見えた。
そして、いつものようにぼくとおじいちゃんは、おばあちゃんのお墓の前で手と手を合わせながら、おばあちゃんに心でお話を終えて歩き出した。
本堂の前まで来ると『藤井先生』と会った。この『藤井先生』という人はおじいちゃんとパパが一番可愛がっている大切な先生だ。
「おはようございます!」『藤井先生』にぼくは大きな声で挨拶をした。ぼくの声に気づいた『藤井先生』もおじいちゃんとぼくに「おはようございます!」と元気な挨拶をしてくれた。
ぼくは『藤井先生』の笑顔と明るい性格が大好きだ。『藤井先生』は人より早く起きて町を掃除したり、仕事場でもいつも一番早く来て掃除や準備をしている。
ぼくもよく「だっこ」をしてもらったり、いろいろと遊んでもらう。体が大きくとても頑丈な『藤井先生』とよくする遊びは、ぼくと『藤井先生』が向かい合って手をつなぎ、ぼくが『藤井先生』の足元からおなかにわたって上り、後ろに空中バック回転をさせてもらうことだ。普通の大人だったら一回転しかできないけれど、藤井先生だといつも連続で5回もできる。この空中バック回転ほど気持ちのいいものはない。ぼくが『藤井先生』のことを大好きだということは、おじいちゃんもよくわかっている。
おじいちゃんは、同じお仕事をしている人の中でも『藤井先生』に対してだけはいつも「藤井さん!藤井さん!」といって特に親しみ、頼りにしている。おじいちゃんとは対照的に一滴のお酒も飲まないのだけれど、お弟子さんの中では一番可愛がっていて、性格的にもとても相性が合うのだと思う。二人の間には、とても大きな信頼関係があることがぼくにもよくわかる。
『藤井先生』の指圧技術が素晴らしいところ、人間的にとても思いやりがあるところ、そして仕事を一生懸命するところをおじいちゃんはよく知っている。おじいちゃんもパパも『藤井先生』が一番の弟子だと口をそろえていう。
ぼくは、おじいちゃんにたずねてみた。「何でおじいちゃんは『藤井先生』のことが大好きなの?」ぼくの質問におじいちゃんは「藤井さんはとうめいな人だからだよ!」「とうめいな人ってどういう人なの?」ぼくは聞いた。「とうめいな人とは透きとおった心で、不必要な欲を持たない綺麗な生き方の人をいうんだよ。」ぼくから見ても『藤井先生』は裏表がなく、本当に心の綺麗な人だと思う。
さらに、おじいちゃんはいった「わしも藤井さんを見習わなければいかんな。」と。そういったおじいちゃんはぼくから見て、とっても「とうめいな人」に見えた。
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
元旦は、おじいちゃんとぼくは『初日の出』を見に愛宕山に行く。ぼくたちが一年の一番初めにすることは、ここから『初日の出』を見ることだ。
おじいちゃんは、東京タワーを真横に見ることのできるこの愛宕山が大好きだ。ここは都会の中でも、おじいちゃんお気に入りの絶景の場所でもある。
『初日の出』のご来光を見ようと人々が集まってくる。東の地平線からゆっくりと太陽が昇ってくると、おじいちゃんは手を合わせ『初日の出』に向かって願い事をしている。ぼくも手を合わせて、おじいちゃんがいつまでも元気でいてくれるようにとお願いする。そして家族、仲のいいお友達が健康でよい年になるように心からお願いをする。
太陽がだいぶ昇ってくると、ある男の人の周りに、人が輪をつくって囲んでいることに気がついた。おじいちゃんもぼくの手をとってその輪に加わった。すると「浪さん、明けましておめでとうございます!」と輪の中心の男の人が、おじいちゃんに新年の挨拶をした。おじいちゃんも「明けましておめでとうございます。馬琴さん、今年もよろしくお願いしますね。」と挨拶をした。どうやら、このおじさんとおじいちゃんは友達のようだ。
おじいちゃんは「孫も一緒に連れてきたので、よろしくお願いします。」とそのおじさんにいった。ぼくはどこかでこのおじさんを見たことがあると思ったら、講談師の『宝井馬琴師匠』だった。
しかし、いつもテレビで見るときよりも、今日は一味違っていた。良く見てみると馬琴師匠の手には『日本刀』が持たれている。ぼくは一瞬びっくりした。
すると、いきなり輪の中心にいる馬琴師匠は「いやーっ!」と気合の入った声とともに『日本刀』を一気に抜いた。『初日の出』のご来光をうけた『日本刀』はキラキラと光輝いている。それはなんと美しいことであろうか、ぼくはあまりの美しさと驚きに、言葉を失った。
そして、馬琴師匠のお話が始まり、周りの人たちはみんな、静かに固唾を呑んで聴いている。師匠は振りかざした『日本刀』の歴史と、『初日の出』を見る心構えと心のあり方をゆっくりと静かに語っている。ぼくの目の前でお話をしている師匠は、さぞ重いであろう『日本刀』をなおも力強く振りかざし、お話を続けた。
ぼくの目の前に、キラキラと光る『日本刀』が近づいてきた。ぼくは無意識のうち、とっさにその『日本刀』に触ってしまった。冷たく鋭い刃が見事な触感だった。すると、横からおじいちゃんがぼくの手を握り、静かに『日本刀』からぼくの手を遠ざけた。ぼくは、おじいちゃんのその素早い軽やかな動きに驚いた。
おじいちゃんはぼくと手をつなぎ、足早に輪から離れた後で、ぼくにいった。「ター坊、二度と『日本刀』に触れてはいけないよ!『日本刀』というやつは軽く触っただけで、指なんか軽くとれてしまうぐらいの切れ味を持っているのだから!」いつになく、おじいちゃんの表情は真剣そのものだった。
そのあと、おじいちゃんは輪に向かわず、ぼくの手をとり明治神宮に初詣に行った。おじいちゃんにとっては、愛宕山での一件がよほどショックだったらしい。参道の砂利道を歩きながらも、ぼくにはおじいちゃんの心が手にとるように分かった。
ぼくはおじいちゃんに謝った。「おじいちゃん、さっきはごめんなさい。もう二度と『日本刀』に触ったりしないからね!」するとおじいちゃんはいった。「ター坊の指が削げないで本当によかったよ!実はあの瞬間、おじいちゃんは心臓が止まるくらい驚いたんじゃよ。これからは絶対におじいちゃんを驚かせるようなことはしないでおくれよ!」
そしてお賽銭箱に、おじいちゃんは100円、ぼくは5円玉を投げ入れた。ぼくは願った。もっともっといい子になって、おじいちゃんに心配をかけない立派な人間になるんだってことを。
生まれて初めて『日本刀』に触れ、『日本刀』の冷たさがいつまでも指に残っていたとっても寒い日のことだった。 |
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
ぼくには、秋から冬にかけてとても楽しみなことがある。それは伝通院さんの大きなイチョウの木にたくさんの『ぎんなん』の実ができることだ。
この日も、朝早くからおじいちゃんとぼくは地面一杯に落ちている『ぎんなん』の実をビニール袋一杯に拾い集めに行った。多いときには二人で100個以上は拾ってしまう。おじいちゃんは「この伝通院さんのイチョウの木は女の人なのさ。だから実をたくさんつけることができるんだよ。」と教えてくれた。「人間も赤ちゃんを生むことができるのは女の人だけど、イチョウの木まで実をつけるのが女の人だとは驚きだね!」とぼくはおじいちゃんにいった。「さてター坊、帰ってタックのおばちゃんとママに報告しに行こう。」ぼくは「うん!」と大きな声で返事をした。
家に帰って、タックのおばちゃんにたくさんの『ぎんなん』を見せると、おばちゃんは目をパチくりさせて驚いていた。ママも「まー、たくさん拾ってきたのねー!」といいながら、「早速乾かさなきゃ。」といって裏の玄関から外に出て行ってしまった。しばらくして見に行くと、新聞紙の上にのせられた『ぎんなん』がとてもかわいらしく並べられていた。
数日後、晩ごはんの時にきれいなみどり色の『ぎんなん』が出てきた。おじいちゃんは「最高のビールのおつまみだな!わっはっはー。」といって喜んでいる。パパも上機嫌でおじいちゃんと乾杯をして、ぼくとおじいちゃんが拾ってきた『ぎんなん』をおつまみにビールを飲んでいる。ぼくはおじいちゃんとパパが楽しそうにビールを飲んでいる姿を見て、ぼくも早く二人といっしょにビールを飲みたいなと思った。
ぼくはおじいちゃん、パパ、ママ、タックのおばちゃんといつまでも、このままこのおうちに一緒にいたいと心から思う。どちらかというと、おうちは古くてそんなにきれいとはいえないけど、たくさんの人が集まってきて、あったかくて優しさと思いやりが一杯あふれている、最高のぼくのおうちだから。
次の日の朝、おじいちゃんは「ター坊、今日は『渋谷のおばあちゃんの家』に行こう!」そういうと、乾かし終わった殻のついた『ぎんなん』をたくさん紙袋に入れておうちを出発した。
渋谷のおばあちゃんとは、ママのお母さんのことで名前は『おとめ』という。おじいちゃんは、いつもぼくと一緒のことが多いので、たまには渋谷のおばあちゃんにぼくの顔を見せてあげようといって連れて行ってくれる。でもぼくが不思議だなと思うことは、おじいちゃん同士は飲み友達で、とても仲がよいのに、どうして『渋谷のおじいちゃんの家』といわないで『渋谷のおばあちゃんの家』というんだろう?ということだ。とても不思議だ。
『渋谷のおばあちゃんの家』に着き、お土産の『ぎんなん』をわたすと、おばあちゃんは「あらまあ、こんなにたくさんありがとう。重かったでしょう。」と優しい声でいう。おじいちゃんは「おとめさん、ター坊と拾ってきた伝通院の『ぎんなん』だから『ひろみつ』さん(渋谷の祖父のこと)と食べてくださいね。」といった。ぼくは、おじいちゃんのそんな小さい優しさが、とても大好きだ。おばあちゃんもそんな『ビールじーじ』の優しさを、いつも「とってもうれしい。」とぼくにいう。
渋谷のおばあちゃんにさよならをして、帰り道を歩きながら、おじいちゃんはいった。「なあ、ター坊、渋谷のおじいちゃんとおばあちゃんにとってはター坊が初孫だからとても可愛いんだよ。これからも時々顔を見せてあげるんだよ!」。ぼくはこの時、おじいちゃんは本当に素晴らしい人だと思った。こんなに優しい心を持っているおじいちゃんの孫で本当によかったと。
ぼくはいつか自分がおじいちゃんになった時、ぼくがおじいちゃんから教わったことと同じことを、ぼくの孫に教えてあげたいと思う。 |
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
今日はおじいちゃんが『後楽園ゆうえんち』に連れて行ってくれるというので、ぼくは朝からうきうきしている。ぼくのおうちから『後楽園ゆうえんち』までは歩いて5分くらいの距離でとても近い。
おじいちゃんとぼくは途中、『礫川公園』の中を抜けて行く。ここには戦争で亡くなった人たちの戦没者霊園があっておじいちゃんは両手を合わせ大きく一礼し、戦争で亡くなった方への哀悼の気持ちを伝えている。すさまじいくらいのせみの鳴き声があちらこちらでする。ぼくはブランコと鉄棒をちょっとだけする。階段を降りる途中の植え込みはまるで迷路のようになっている。
この前は『カマキリ』の卵をみつけて、おうちに持って帰り虫かごに入れたまま玄関においていたら、数日後、ものすごくたくさんの『カマキリ』の子供が卵の殻を破って出てきていて、ぼくは腰が抜けるほど驚いた。ママに見せると「キャーッ!」と悲鳴を上げ、すごい形相で「表に逃がしてきなさい!」としかられた。ぼくはすぐに、できるかぎり、ちっちゃな『カマキリ』の子供を洗面器に入れて『礫川公園』に返しに行った。そんなわけでこの『礫川公園』はぼくにとっては自分の家の庭のような大切な場所だ。
ブランコと鉄棒をやり終えると、おじいちゃんは「ずいぶん、さかあがりがじょうずになったもんだな。たいしたもんだ。」とほめてくれた。そして『後楽園ゆうえんち』に着き、入場券を買って中に入ると最初に行くのは車に乗って行くほうの『お化け屋敷』だ。これはおじいちゃんと二人で座って乗れるので怖くなく楽しく見れる。
表に出て今度は本当の『お化け屋敷』に入る。今度は自分の足で歩いて回るのでちょっと怖いが、勇気を出しておじいちゃんと入る。何人か他の子供たちも並んで入った。ぼくはおじいちゃんの手をしっかりと握りながら真っ暗の中を歩く。薄気味悪い『お化け』がいっぱいいる。この異様な怖さといったらないのに、後ろから子供たちが「ギャー、出たー!」といって、ぼくとおじいちゃんの間をすり抜けて行った。すると、本物の『お化け』が近寄ってきたのでぼくもとっさに逃げ出した。「おじいちゃん、助けてー。『お化け』が出たー!」ふと気づくとぼくの隣にいたおじいちゃんがいない。ぼくは『お化け屋敷』の道をへんなところに迷い込んでしまったみたいで、ひとりぼっちになってしまった。
「おじいちゃーん!どこー!」真っ暗の中、おじいちゃんの声はない。ぼくは心細くなってしまいベソをかいていると、なんとさっきの『お化け』が出てきた。「ギャーッ!助けてー!」ぼくは大声で叫んだ。その時、『お化け』がぼくの手をとり歩き出した。もうダメだと思い、ぼくは観念した。すると『お化け』は出口までぼくの手を引き連れて行ってくれたのだ。
なんと、『お化け屋敷』の中で迷子になったぼくは『お化け』に助けられたのだ。外に出るとおじいちゃんがぼくを待っていてくれた。「おじいちゃーん!『お化け』に助けてもらったよ。」ぼくがいうとおじいちゃんは「ター坊とはぐれてしまってびっくりしたよ。出口にいれば会えると思っていたんじゃが親切な『お化け』でよかったなあ。わっはっはー」といって大笑いしている。
ぼくは喜んでいいんだか、なんだか複雑な気持ちだった。それにしても生まれてはじめて『お化け』に助けてもらった、とても不思議な日だった。 |
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
いつものように、おじいちゃんと散歩をしていると、おじいちゃんはいった。「なー、ター坊、バイキングに行かないかい?」ぼくは聞き返した。「バイキングって海賊か何かのことでしょ?」するとおじいちゃんは「そのバイキングとは違って、いろいろな料理がたくさんあって、何をどれだけ食べてもいいところが、バイキングというんだよ。」
ぼくは「それはいいね!どこで食べれるの?」とおじいちゃんに聞いた。「新しく建ったホテルニューオータニのタワー40階にあるのさ!見晴らしはいいし、おいしいし、天気がよければ富士山だって見えるんだよ。」おじいちゃんはさも詳し気にいった。
ぼくはそんな話を聞いてしまったから、急におなかが「グウーッ!」と鳴り出した。「おじいちゃん、バイキングに連れてって!おなかすいたよ!」そうぼくがいうのを待ってましたとばかりにおじいちゃんは「よーし、それじゃ大曲から飯田橋をぬけて、お堀沿いを歩いて、迎賓館の前を通るコースで行こう!」「やったー!レッツゴー!」ぼくらはさっそく、伝通院さんを出発した。
大曲を抜け飯田橋の歩道橋を歩くと、下を流れる神田川にきれいなコイがたくさん泳いでいるのが見える。歩道橋を降りると、お堀のお水がキラキラとまぶしく光っている。朝早いので、ボート乗り場のボートは行儀よく整列しているように並んでいる。市ヶ谷の釣堀を見下ろしながら歩く道は、とても静かでまっすぐだ。四ッ谷の手前で、野球場とテニスコートを過ぎると大きなカーブが左へと続いている。カーブが終わるとすぐ四ッ谷の駅があって、迎賓館が正面にみえる。堂々としていていつ見ても立派な建物だと思う。左の下には上智大学の運動場があり、その先の道を左に曲がると右側にホテルニューオータニが見えてきた。
入り口を入って、とにかくまっすぐ突き当りまで進むと右側の40階まで行くエレベーターに乗る。そして一気に40階まで上る。エレベーターはとても早くて、耳がツーンとしてきた。
おじいちゃんとぼくがバイキングの入り口に行くと、案内してくれるお兄さんが窓際の席に連れて行ってくれた。外を見るとすごい景色にびっくりした。
東京中の空を一人じめしたような感じだ。下を見るとなおさら高いのが分かって足がすくんでしまう。おじいちゃんが遠くを指差し「ほら向こうに富士山がよく見えるよ!やっぱりいつ見ても日本一の山だな。」と富士山に見入っている。
「おじいちゃん、おなかへったからバイキング食べようよ!」というと「おう!そうだった。食べよう。」といってたくさんお料理が並んでいるところにぼくを連れて行ってくれた。種類は30種類くらいあるだろうか、洋食、和食、サラダ、ジュースなど、どれもこれも食べたいし、飲みたい。ぼくはバイキングを5回くらいかわるがわる取りに行って、いろいろなものをいっぱい食べた。
おじいちゃんも満腹になったみたいで、コーヒーを飲んでゆっくりしている。するとおじいちゃんは席を立ち「ター坊、もう一回行こう!」という。「ぼくはもう満腹で食べられないよ!」そうおじいちゃんにいうと「OK!わかった。」といってバイキングを取りに行ってしまった。
すぐおじいちゃんは帰ってきたけれど、お皿を持っていない。手には、なにやら紙ナプキンに包んだものを持ってきて「これなんだか分かるかい?」とぼくに聞く。
「いったい何を持ってきたの?教えて!」というとおじいちゃんはその紙ナプキンを自分の洋服のポケットに押し込んだ。「よし、それじゃおなかも満腹になったことだし、下の庭でも散歩しよう!」そういうおじいちゃんは、とにかくニコニコして、なにやらウキウキしている様子だ。
エレベーターでロビーに着くと、長い廊下の途中からお庭に出れるようになっている。大きな池と滝があり、本当の庭園だ。
庭の途中に池をまたいで、赤い橋がかかっている。おじいちゃんは、その橋の真ん中で立ち止まると、さっきポケットに突っ込んだ紙ナプキンを取り出した。すると両手で紙ナプキンをもみしだきながら、ぼくの顔をにっこりと見た。
おじいちゃんは静かに紙ナプキンを開くと、中から出てきたのはなんと、バイキングのパンのところにあったチーズをのせて食べるクラッカーだった。 そして、バラバラになったクラッカーをぼくの手のひらにのせると「池に向かって投げてごらん。」といたずらっ子のような顔でいった。
ぼくは迷わずに、池にクラッカーを投げ入れると「バシャ!バシャ!バシャ!」一気にコイが集まってきて、われ先にとクラッカーを食べている。おじいちゃんは、ぼくにこれを見せたくて、紙ナプキンにクラッカーを入れて持ってきたんだってことがやっと分かった。
おじいちゃんは、次から次へとクラッカーを投げ入れるぼくを見てニコニコ笑っている。おじいちゃんはそうやっていつもぼくのよろこぶ顔を見て笑っている。ぼくはそんな優しい笑顔のおじいちゃんがとても大好きだ。
ぼくはおじいちゃんにいった。「また、バイキングに連れてきてね!約束だよ!」 |
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
おじいちゃんは大好きな映画を観る時は、決まって銀座の映画館だ。
おじいちゃん曰く、「映画を観る時は、大きな映画館の大きな画面で観るのが迫力があって大好きだな!」と。その中でも『日比谷映画劇場』といって、果てしなく広く2階席3階席が上にまで急な角度で広がっているところがある。すごく大きな画面で観る迫力はここが一番だ。
この映画館には、近日公開の映画のチラシがいっぱい置いてあって、おじいちゃんとぼくは一緒に集めている。映画のパンフレットは、入り口で必ず買ってから入る。混んでいるときは、指定席の白いカバーをかぶった席で観るのが、おじいちゃんは好きだ。映画が始まる前の白黒のニュースも、面白くてぼくは真剣に観てしまう。
映画が終わって、『日比谷映画館』を出ると、すぐ左脇に階段があって、地下に降りていくとポスターや写真をいっぱい売ってるお店がある。おじいちゃんはそのお店に入ると、飾ってある金髪の女優さんのポスターを眺める。その表情は、にこやかでとても輝いて見える。
そして、「ター坊、このポスターの『マリリン・モンローさん』は本当にきれいな人だったよ!顔もからだも本当に天使のようだったよ!」とぼくにいった。
ぼくはおじいちゃんに「何でおじいちゃんそんなこと知ってるの?お友達だったの?」とたずねると「おじいちゃんは、ター坊が生まれるずーっと前の昭和29年に『モンローさん』を指圧したことがあるんだよ。すごく喜んでもらって7回も帝国ホテルに呼ばれて指圧したんだよ。」とおじいちゃんは満面の笑みでお話をしてくれた。
「おじいちゃんすごいね!こんなポスターになるような人を指圧するなんて。アメリカでも有名な人なの?」とぼくが聞くと、おじいちゃんはポスターの中にいる『モンローさん』に語りかけるように「世界中の人が憧れていた世界一の女優さんなんだよ。でも残念にも、ター坊が生まれる前の年に亡くなってしまったんだよ。」そう話してくれたおじいちゃんは、遠くを見るような目で悲しい顔になった。
ぼくにはおじいちゃんにとって、『モンローさん』はとても大切な人だったということがとてもよくわかった。
店の階段を上り、表に出ると『みゆき通り』に向かって歩く。『有楽座』の手前の細い道のむこうでは、ゲームの大きな音がしている。『有楽座』ではチャップリンのリバイバル映画をやっている。道は女の人であふれかえっている。ちょうど『宝塚のショー』が終わる時間とぶつかったからだ。
『みゆき通り』に出ると、おじいちゃんは「ター坊、帝国ホテルによっていこう!おじいちゃんはビールを一杯だけ飲みたいな。」といった。そして一階の大きなラウンジでおじいちゃんはビールを、ぼくはレモンスカッシュを注文した。
「この帝国ホテルでおじいちゃんは、ハネムーンで宿泊していた『モンローさん』を指圧したんだよ!」おじいちゃんは誇らしげにいった。ぼくはさっきの『モンローさん』のポスターが頭から離れない。
「おじいちゃん、それにしてもさっきのポスターの人きれいだったね!」ぼくがそういうと、「本当にきれいだったよ!しみひとつ無いからだで、すばらしい弾力だったよ。つやつやの肌で、あんな完璧なからだの女性は、あとにもさきにも初めてだったよ!」ぼくは驚いた。何でおじいちゃんはそんなこと知っているんだろう。
ぼくは勇気を振り絞って聞いてみた。「おじいちゃん、なんでそんなこと知っているの?あの女の人の『裸』を見たことあるの?」ぼくは胸がどきどきして、手に汗をかいている。おじいちゃんは平然とした顔で、ぼくにいった。「バスローブの下は『裸』で『シャネルの5番』だけを身につけていたさ。でも『モンローさん』を指圧することだけしか考えられなかったよ。」
「日本では普通、ガウンを着て指圧をするけれど、アメリカではマッサージを受けるときは『裸』だから、『モンローさん』は指圧のときも『裸』だと思ったんじゃないかな。でもおじいちゃんは指圧の名人だから、世界一の美女だからって、そんなことにはぜんぜん動揺しなかったさ!それが真の指圧師というものだよ!」というと、豪快にいつもの笑い方で「ター坊も大きくなったら、おじいちゃんのお仕事のお手伝いをしておくれよ!なんたってター坊は三代目なんだからな。わっはっはっはー!」といった。
ぼくは、そんなこと急にいわれても困るよと思ったけれど、おじいちゃんがいってくれた言葉を胸にしまった。おじいちゃんが、ぼくのことを本気で三代目と思ってくれているという気持ちだけでうれしくて、おじいちゃんの気持ちを大切にうけとめた日だった。 |
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
ぼくは生まれたとき『2000グラム』しかなく、未熟児として生まれてきた。
ママは妊娠中毒症になってしまい、ママかぼくのどちらかしか生きられないだろうとお医者さんはいったそうである。
やっとの思いでぼくが生まれてきたそうだが、仮死状態で衰弱しているぼくを見て、パパは「どんなことがあってもこの子を元気に育ててみせる。それが親としての務めだ。」といってママを励まし、元気づけたそうだ。
おじいちゃんもママに「こんなに小さい身体で生まれてきても、しっかりと自分で呼吸して頑張って生きているんだから、この子は生命力がとても強い子だ。絶対、元気に育つから大丈夫だよ!」といってくれたそうだ。
その時のその言葉が、ママはとても嬉しくて、だから『頑張れた』と話してくれた。
ぼくのおじいちゃんとパパは『指圧』というお仕事をいっしょにしていて、ぼくが生まれたときからずっと毎日毎日、未熟児のぼくに『指圧』をしてくれたおかげで6ヶ月で普通の赤ちゃんと同じ標準体重になったそうだ。ぼくはおじいちゃんとパパに『指圧』で助けてもらったのだということにとても感謝している。
ぼくが生まれたときのことを、パパはよくこう話してくれる。「本当に小さく生まれてきたから、生まれた時は心配で、いても立ってもいられなかった。でも『指圧』をやっていて本当によかったよ。お前が今、元気でいられるのはみんなおじいちゃんのおかげだな!」と。ぼくはそれだけ小さく、危険な状態で生まれてきたのだろう。
ぼくのおじいちゃんは『指圧』という、薬や器具を使わずに親指と手だけで、人の身体を元気にするお仕事を考え出した人だ。
おじいちゃんには子供が3人いて、ぼくのパパだけが、おじいちゃんといっしょに『指圧』のお仕事をしている。
そんなわけで、兄弟の中でも、パパはおじいちゃんのことを父親としてだけではなく『指圧』の師匠としても、とても尊敬している。また、おじいちゃんもパパのことを「かえるの子はかえるだ!子供は親の背中を見て育つ。わっはっはー!」と笑いながらいつも口癖の様にいう。
ぼくの身体全体には『おじいちゃんの手』と、『パパの手』の感触が赤ん坊のときからしみついている。
『おじいちゃんの手』は大きくてマシュマロのようにやわらかく、親指はつきたてのお餅のように弾力があって、『指圧』をしてもらうと押してもらったところから身体全体に血液がいきわたるのが分かり、身体がぽかぽかして暖かくなる。そして、心がとても安心した気持ちになる。
『パパの手』はとても分厚くて、親指はスーパーボールを粘土でおおいつくしたように頑丈な親指で、『指圧』をしてもらうと筋肉の深いところまでジンワリと指のぬくもりがしみわたる。そして、やわらかく頑強な指の感触が、手の先や足先まで広がり、身体全体に元気があふれてくる感じになる。
世界で一番と二番の『指圧名人』に、毎日『指圧』をしてもらえるのは地球上で、たった一人。もちろんぼくだけだろう!
それにしても『指圧』ってほんとに不思議だなと心から思う。それはおじいちゃんとパパがぼくに『指圧』をしてくれているとき、たくさん感じることができる二人の気持ちだ。
「元気になーれ!」「丈夫に大きく育て!」という、ぼくをとても大切に思ってくれている二人の気持ちと願いが、親指からぼくの心に響き伝わってくる。不思議だけれども、おじいちゃんとパパの暖かくて優しいぼくへの気持ちが『指圧』を通して、そう感じさせてくれるのだと思う。
『2000グラム』で生まれた未熟児のぼくが元気でいられるのも、おじいちゃんとパパのおかげであり、二人に対する気持ちと同じくらい『指圧』にも心から感謝している。
ぼくが大人になったら、今度はおじいちゃんとパパに、元気で長生きしてもらえるように、毎日指圧をしてあげたいと思う。
 |
 |
| 2000グラムの未熟児として産まれる(S38.4.11) |
 |
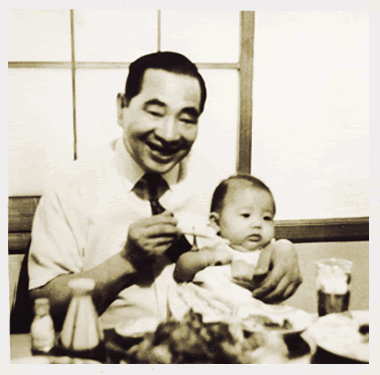 |
 |
| 生後百日のお食い初めを無事に迎える(S38.7.19) |
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
みゆき通りの『たいめい小学校』の近くに『鳳鳴春』という中華料理のお店がある。ここはおじいちゃんお気に入りのお店だ。
おじいちゃんはビールとピータンとくらげを、ぼくは中華丼を注文する。このお店の中華丼には、お肉やたけのこが沢山入っているので、ぼくの大好物のひとつだ。おじいちゃんもビールがすすんでくると、マーボ豆腐やチンジャオロースを追加し、テーブルの上には、ぼくら二人の大好きなものが並んだ。
しばらくすると、おじいちゃんは「ビールはこれぐらいにしよう!」といい、お店の人に何かを頼んだ。そのあとおじいちゃんの頼んだお酒がテーブルの上に運ばれてきた。白い器に入っている『お酒らしきもの』は、いったい何なのだろう?いつもおじいちゃんが飲んでいる日本酒やウイスキー、ブランデーとも違う形の器から注がれたものを、ぼくはじっと見ていた。
すると、おじいちゃんは「おい、ター坊、このお酒は『ラオチュウ』という中国のお酒なんだよ。アルコール度数が70度くらいあって普通の人が飲んだらひっくり返ってしまうほど強いお酒なんだよ。」といった。
ぼくはそれを聞いて「おじいちゃん、そんなお酒を飲んだら危ないよ。おじいちゃんがひっくり返ったら困るからやめて!絶対だめだよ!」といった。ぼくの頭には、日本酒を飲んでぶっ倒れている『タックのおばちゃん』の姿がよぎったからだ。
おじいちゃんは、そんなぼくを見ながら、いつもの恵比寿様のような顔で笑っている。まったくなんだっておじいちゃんといい、パパといい、『タックのおばちゃん』といい、大人はお酒なんか飲むんだろう?
何が楽しくて何がいいのか、ぼくにはまったく理解ができない。おじいちゃんやパパがぶっ倒れたのは見たことがないけれど、ここでおじいちゃんがもし倒れたら、ぼく一人ではおうちに絶対運べない。そんなことを頭の中で考えていると、おじいちゃんはお店の人を呼び「申し訳ないけれど、マッチをひとつ持ってきてくれないかな?」といった。
おじいちゃんはタバコが大嫌いな人なので、タバコは吸うようなことは絶対にない。ぼくはいったい何のためだろう、と不思議に思っていると「ター坊、よーく見てるんだよ!」といい、注がれたグラスにマッチの火を近づけた。その瞬間、青い炎が静かにグラスの表面をおおった。その炎は静かに、優しくともっている。「ふうーっ!」とおじいちゃんが息を吹きかけると青い炎は消えた。「すごいね!おじいちゃん。お酒に火がついたよ!」ぼくは本当にびっくりした。
とても驚いているぼくに、おじいちゃんはいった。「ター坊、このことはパパやママには絶対内緒だぞ。二人だけの秘密だよ!」そういったおじいちゃんは、マッチを持ってきてくれたお兄さんに「ありがとう」といってマッチを返しウインクすると、さっきまで火がついていたグラスを一気に飲み干した。
「やられたー!」と思った瞬間の出来事だった。しかしおじいちゃんはケロッとしている。「おじいちゃん、大丈夫?」とぼくが聞くとおじいちゃんは「なーんじゃらほい!わっはっはー!」といって、いつもの大笑いをしている。
ぼくは胸をなでおろした。こんな『やんちゃ』なことをするおじいちゃんだけれど、ぼくにとっては一番のおじいちゃんだ。そして一番の友達でもある。
そんなおじいちゃんに、ぼくもいった。「おじいちゃんのこと心配して損しちゃった。なーんじゃらほい!」 |
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
銀座に『伊東屋』という大きな文房具店があって、おじいちゃんは原稿を書くための筆記用具などをよく買いに来る。
このお店はビルになっていて、その全部で文房具用品を扱っている。会社や学校で使うものはすべてそろい、クレヨンや24色の色鉛筆などもあるので、ぼくにとっても大切なお店のひとつだ。
買い物をすませたおじいちゃんとぼくは、お店の前に出た。お店の前は銀座の大通りがまっすぐに、どっしりとずっと先の方まで見える。おじいちゃんは「ター坊、日本橋まで歩かないかい?」とぼくに尋ねた。もちろんぼくも「うん、いいよ。歩こう!」と答えた。
銀座一丁目にある『テアトル東京』という映画館の、『ゴッドファーザー』シネラマと書かれた大きな看板の前を通り過ぎると、あっという間に日本橋の『高島屋』についた。
「今度はター坊の番だな!」おじいちゃんは自分が買い物したあとは、必ずぼくの行きたいところにも連れて行ってくれる。
毎回何かを買ってもらうわけではないけれど、おじいちゃんはぼくの心の中が分かるんだと思う。そして、ぼくたちは『おもちゃ売り場』へ向かった。
特にお気に入りなのは、電車の車掌さんが持っている『切符切りセット』だ。ビニール袋の中には切符切りと乗車券がたくさん入っている。他には『ウルトラセブンのウルトラアイ』や、『ウルトラ警備隊の腕時計型通信テレビ』だ。『おもちゃ売り場』を見ていると本当に胸がわくわくしてしまう。
ふと、横にいるはずのおじいちゃんの方へ目をやると、そこにいるはずのおじいちゃんがいない。ぼくはあちこち、行ったりきたりして探してみたが、広い『おもちゃ売り場』のどこにも見当たらない。
ぼくは急に悲しくなってしまい、大粒の涙が次から次へとこぼれてきた。このまま本当に会えなくなってしまうのではないかと思うと、なおさら涙が止まらない。
とりあえずエレベーターガールのお姉さんに事情を話して、おじいちゃんを探してもらおうとエレベーターの前に行った。すると遠くのほうから、おじいちゃんが僕の知らない『男の子』と手をつないで、こちらに歩いてくるのを見つけた。
ぼくは走って「おじいちゃーん!!」と大きな声でおじいちゃんのからだに抱きつくと、おじいちゃんは「おやっ?」といった表情で手をつないでいる『男の子』の顔を確かめるように見た。
するとびっくりした顔で急に、その『男の子』の手を離し、ぼくの手をとり、足早に『おもちゃ売り場』から離れた。おじいちゃんは、ぼくと間違えて、知らない『男の子』と『おもちゃ売り場』を見て回っていたらしい。
ぼくはおじいちゃんに尋ねた。「おじいちゃん、さっき手をつないでいた『男の子』って誰なの?」するとおじいちゃんは「手をつないできたものだから、てっきりター坊だとばかり思っていたんじゃが、どうやら知らない子だったようじゃな!」と苦笑いをしながら言った。
でもぼくは、おじいちゃんに会えて本当によかったと胸をなでおろした。そしておうちに帰ってパパとママに『おもちゃ売り場』でおきた話をすると、パパは「それでそのおじいちゃんと手をつないでいた『男の子』はちゃんと親と会えたんだろうね?」と聞いてきた。ぼくはパパのその問いに「ぼくはおじいちゃんと会えた事しか考えてなかったから、わからない。」と答えた。 パパは少し呆れ顔でママに言った。「本当に親父さんには困ったもんだな!」
ぼくは思った。これからおじいちゃんと歩くときは、今まで以上におじいちゃんの手をしっかりと握って歩くことを…。
そのあと、お風呂に入ってお布団で寝るときに、パパの話していたことを急に思い出して、なぜか心配になった。あのおじいちゃんと手をつないで歩いていた『男の子』も家でいつもどおり寝てるかなと…。
その日、ぼくは名前も知らない、あの『男の子』の無事を願って眠りについた。 |
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
ぼくのパパは長男だから、おじいちゃんのお仕事をついで『指圧』というお仕事をしている。
ぼくのパパは、日本の大学を卒業すると『アメリカのメディカルスクール』に留学し、卒業後もアメリカで指圧の普及活動を続け、7年間アメリカで生活していた。本当はアメリカにずっと住んでいたかったらしいが、おじいちゃんがパパに、跡継ぎとしてお仕事を手伝ってほしいということで、日本に帰ってきたそうだ。
おじいちゃんは、パパが『金髪の女性』を連れて帰ってくるんじゃないかと、とても期待していたらしい。ところがおじいちゃんの期待とはうらはらに、パパは一人で日本に帰ってきたそうである。そんなパパに結婚の話が持ち上がったのは、おじいちゃんの仲のいい飲み友達の『高浪のおじさん』と二人で、おじいちゃん行きつけのお店『ぎょくせん』でお酒を飲んでいたときだそうだ。
『高浪のおじさん』の大学時代の親友に、素晴らしいお嬢さんがいるから、徹ちゃん(ぼくのパパ)に会わせたいとのことで、まずは当人同士を会わせる前に二人の『親父さん』同士を会わせてお酒を飲んだところ、意気投合し、いやはやなんと、そのときに結婚させることを親同士が勝手に決めてしまったとのことだ。その二人の『親父さん』というのが、ぼくのおじいちゃんたちだったわけである。
そして当人同士を会わせたところ、本当にとんとん拍子に話がまとまって、結婚したそうだ。ぼくは、さすが『高浪のおじさん』だなと思った。恋のキューピットというよりは、からだも大きく声も低くて、『野武士』のような人だけれど、この『高浪のおじさん』がいなかったら、ぼくはこの世に生まれていなかったのかと思うと、人間の縁というのはとても不思議なものなんだなと思う。
ぼくのおじいちゃんは、『高浪のおじさん』のことを「本当に男らしい人だ」といつもいう。おじいちゃん曰く、「『高浪のおじさん』という人は、絶対にうそをつかないし、絶対に陰口や人の悪口をいわない。人から聞き伝えに聞いたことよりも、自分が見たことで正しい判断をする。そして本当にいいたいことは、本人の前ではっきりという。ター坊も『高浪のおじさん』のように立派な大人になっておくれよ!」
ぼくは、おじいちゃんの言葉を聞いて、『高浪のおじさん』がぼくの二人のおじいちゃんたちとずっと、仲のいい共通の友達でいられるのは、『三人』とも純粋で、思いやりがあって、決して人にうそをつかず、人の悪口をいわない『まっすぐな人間』だからだ、とつくづく思った。
ママの方のおじいちゃんから聞いた話では、『高浪のおじさん』は、今だからこそ紳士だけれど、大学時代は誰もが恐れるほどの正義感の持ち主だったそうだ。どんな間違ったことも大嫌いな人で、みんなから一目置かれる存在だったとのことである。
そしてけんかでは、一度も負けたことがないほどの無頼の強さで、そんな『高浪のおじさん』のことを、友達はみんな『けんか日本一の男』と呼んだそうだ。
普段は優しくおだやかな人だけれど、うそをついて人を陥れたりする人間だけは、その人が改心し反省するまで決して許さない。
そのような人間にとっては、とても恐ろしく、怖い人だったらしい。でも『高浪のおじさん』は、相手が反省し悪かったところを改めれば、すべてを水に流して仲良くし、そのあとも徹底的に面倒を見た人なので、まわりからは抜群の人望があった人だと教えてもらった。
やはり、『高浪のおじさん』のただならぬ風貌と、頑丈な大きなからだ、低いドスのきいた声はただものではないと思った。それなのに、絶対に威張ったり強がったりしない『高浪のおじさん』は本当に格好いい。
ぼくが『肩車』というものをしてもらったのも、『高浪のおじさん』が初めてだった。そのときの光景といったら、都電よりもずっと高いように感じた。
ぼくも大人になったら『高浪のおじさん』のように、頑丈なからだを持った笑顔の似合う、思いやりのある優しい人になりたいと思う。 |
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
上野広小路に『松坂屋』というデパートがあって、おじいちゃんは暇があるとぼくを連れて行ってくれる。
ぼくの小石川の伝通院のおうちからは決まってタクシーで行く。
さほど遠くないので、早いときは5分ぐらいでついてしまうぐらいの距離だ。
吉池側の入り口から入るのがおじいちゃんとぼくのルールだ。
なぜかというと松坂屋の入り口には、ぼくの大好きな『ヤドカリ』が鉄の洗面器の中にいっぱい入って売られているからだ。
大きいものや小さいのがたくさんいて、見ているだけですごく楽しい。
たまに『お面』なども売っていて、『鉄人28号』や『ウルトラマン』、『黄金バット』までかっこいいものがそろっていて、とても我慢できない気持ちになってしまう。
でも「ター坊、行こう!」というおじいちゃんの声でデパートの中に入っていく。
そしてエレベーターに乗ると、まっしぐらに屋上へ向かう。
屋上では、ぼくの大好きな『孔雀』たちが元気に羽を広げて、まるでおじいちゃんとぼくが来るのをわかっていたかのように迎えてくれる。
何でこんなに綺麗で美しいのか、いつ来てもぼくは見とれてしまう。
ぼくは、おじいちゃんに尋ねてみた。
「もし、生まれ変われるとしたらぼくは孔雀になりたいんだけれど、おじいちゃんは何になりたい?」
すると、おじいちゃんは言った。
「おじいちゃんは生まれ変わったとしても人間になりたいな。そしてやっぱり『ビール』を飲むことが大好きだと思うな。」
ぼくは少し悲しくなった。
だって、おじいちゃんが人間で生まれ変わったら、ぼくは『孔雀』でおじいちゃんと一緒にいられなくなってしまうと思ったから…。
ぼくが黙って『孔雀』を見ていると、おじいちゃんはいった。
「でもター坊が『孔雀』になるんだったら、ター坊とずっと一緒にいられるようにやっぱりおじいちゃんも『孔雀』になろう。」
ぼくはその『言葉』を聞いたとき、やっぱりおじいちゃんが世界で一番大好きだと強く思った。
しばらくすると、おじいちゃんは「さてター坊、写真を撮ってあげよう!」といって『ションベン小僧』の横に、ぼくを連れて行った。
そして「ター坊、この『ションベン小僧』と一緒に並んでごらん。」といって、写真を撮ってくれた。
その後、『孔雀』にさようならをして、『おもちゃ売り場』を一通り見てから、地下のジュースコーナーで、ぼくはいつもの『メロンジュース』を飲む。
おじいちゃんは『レモンジュース』を飲む。
ここのミキサーで作ってもらった『ジュース』は何でこんなに美味しいのだろう。
この瞬間、ぼくは世界で一番の『幸せ者』だと思う。
それは『ヤドカリ』も『孔雀』も『ジュース』も大好きだけれど、ぼくは『おじいちゃん』と一緒にいられるだけで幸せなのだから。
おじいちゃんにはこれからも、ずっとずっと永遠に『元気』でいてもらいたい。
 |
 |
| 祖父 浪越徳治郎により撮影された「ター坊とションベン小僧」 |
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
銀座のど真ん中に『東京温泉』といって、おじいちゃんの大好きなところがある。
ここはお風呂好きにはたまらないらしい。
お風呂は大きく、サウナや水風呂、ジャグジーなどもあって、さんすけのおじさんが身体を丁寧にきれいに洗ってくれる。
ぼくも洗ってもらった事があるけれど、すごく気持ちがよかった。
サウナには大きなテレビが見れるようになっていて、お相撲のある時などは、たくさんの人で一杯になる。
おじいちゃんは、いつもテレビのまん前で見ている。
だいたい中入り後からは、特に強いお相撲さんが出てくるので、大変なにぎわいだ。
でもいかんせんサウナなので、ずーっと入っていられない人もいて、そんな人は、お風呂の上の階の大広間でガウンに着替え、横になって見る事ができる。
のどが渇くとロビーに行って、ジューサーで作った野菜や果物の入ったスタミナ生ジュースを飲む。
ここの生ジュースを飲むのが、ここでのぼくの楽しみのひとつだ。
お相撲が終わると、もうひとっ風呂入って、おじいちゃんと『東京温泉』から出てくる。
そのあとは、お決まりのコースで、おじいちゃんが一番大好きなビールを飲ませてもらえる銀座7丁目の『サッポロライオンビアホール』に行く。
まずはじめに注文するのは、おじいちゃんは大ジョッキのビールと生ハム。ぼくは、お水とハンバーグ。
そして、二人で乾杯をする。
ここで、生ビールを飲んでいるときのおじいちゃんは、まるで天国にでもいるような顔になっていく。
「ター坊、おじいちゃんは、ここで飲むビールが世界一おいしい。ター坊も、大人になったら、おじいちゃんといっしょに、ここでビールを飲もうな!」
えびす様のような顔になったおじいちゃんは、大ジョッキでいつも5杯は飲みほしてしまう。
ぼくは、おじいちゃんの飲みっぷりと、大ジョッキを持つ大きな手が大好きだ。ほんとうに男の中の男だと思う。
このビアホールの壁画をバックにビールを飲んでいるおじいちゃんは、いつのまにか壁画の主人公のようにも見えてしまう。
ぼくも早く大人になって、この壁画の中でおじいちゃんといっしょに、ビールを飲みたいと思う。 |
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
おじいちゃんの友達に『らかん爺さん』という人がいる。
年はおじいちゃんと同じくらいだけれども、大きく異なる点がひとつある。
それはいつも『裸』だということだ。
ぼくが初めて会ったのは、初めておうちに来たときだ。
紺の海パンのようなもの一丁の姿を見たときは、とてもぶったまげてしまった。(『裸』といっても、紺のパンツだけは、いつもはいている!)
大きな笑い声で笑うところは、ぼくのおじいちゃんととても似ている。
話を聞くところによると、飛行機に乗るときも、『裸』だそうだ。
普通であれば、警察に捕まってもおかしくないところだが、『らかん爺さん』だけは認められているそうだ。
一年中『裸』で、どこに行ってもよいという人は、世界広しといえども、『らかん爺さん』一人だろう。
そんなわけで人々は『らかん爺さん』の事を、『裸王』と呼んでいる。
ある日、ぼくのおともだちの丸ちゃんがこういった。
「ター坊のおじいちゃんが、『裸』で旗を持って歩いていたのを昨日見たよ。旗には全身『顔』にしよう。『裸王』と書いてあったけれど、なにかあったのかい?」
丸ちゃんは本当に驚いた様子だったが、ぼくも真実を伝えなくてはいけないと思っていった。
「実は、良く間違われるんだけれど、その『裸』の人は『おいかわらかんさん』といって、独自の健康法で全身を顔のように『裸』にするのがモットーの、自称『裸王』のおじいさんで、ぼくのおじいちゃんのお友達なんだ!」
ぼくが説明すると丸ちゃんは納得してくれた。でも内心、心の中ではぼくのおじいちゃんが『裸』で歩いていたと思われていたことの誤解が解けてほっとした思いだった。
しばらくしてからこんなことがあった。新年会がおじいちゃんのお友達によってひらかれた。みんな家族をよんでの会だった。
『らかん爺さん』も来ていて、いつものとおり『裸』で「うはっはっはー!ありがたい!ありがたい!」と元気いっぱいだった。
ところが少し離れたところに、ぼくと同じくらいの年齢の女の子が、たった一人でうつむきがちに小さく座っていた。
ぼくは勇気を出して女の子に声をかけてみた。
「ぼくの名前はたかし。通称ター坊。君さっきから一人だけど、家族はどこにいるの?」
女の子はうつむいていた顔を静かに上げ、人さし指で遠くを指さした。
その小さな指先の向こうには、『らかん爺さん』がいた。
女の子は顔を赤らめながら、ぼくにいった。
「私のおじいちゃん、普通のおじいちゃんとちょっと違うでしょ。だから歩くときも、いつも離れて歩くの。今日もパパもママも一緒に来ないから、私だけ一緒に来たの。」
ぼくは返す言葉に困った。
確かに、どこにでもいる普通のおじいちゃんとは、どう見てもいえない。
しかし、とっさに「いやそんなことないよ。ぼくのおじいちゃんも、君のおじいちゃんも、大きな声で笑う笑い方が、人より特徴があって元気なだけさ。ぼくのおじいちゃんなんか、普通の大人の人の、2倍くらいはある大きな親指を前に突き出して立てて、大きな笑い声で笑っているんだよ!人にはそれぞれ個性っていうのが、あっていいんじゃないのかな?」
ぼくと女の子がそんな話をしていると、『裸王』と『親指王』がやってきた。
そして『裸王』が『親指王』にいった。
「おい、なみさん。わしの一番かわいい孫が、今日一緒に来てくれたんだ。こんなことはめったに無いんじゃよ。この子は家にいるのが好きで、わしとは久々に、二人で歩いてきたんじゃよ!」
すると『親指王』が「おじょうちゃん、これからもおじいちゃんを大切にしてあげておくれよ。わしも世界で一番かわいい孫のター坊が、いつも一緒にいてくれるから、元気でいられるんだよ。」
女の子は、大きくうなずいてにっこりと笑った。
ぼくも、おじいちゃんの心からの優しい言葉がうれしくて、今まで以上におじいちゃんを、大切にしようと心に誓った。
ぼくが大人になっても、おじいちゃんの優しい言葉を忘れずに生きていこうと決めた日だった。
ありがとう『親指王』と『裸王』。 |
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
おじいちゃんの親友に、『床屋の二郎ちゃん』という人がいる。
おじいちゃんは『二郎ちゃん』のことを、社長と呼び、『二郎ちゃん』はおじいちゃんのことを、なみさんと呼ぶ。
この『二郎ちゃん』は、おじいちゃんよりも少しばかり年下だけど、ぼくともとても仲がいい。
おうちに遊びにきたときには「おーいター坊、元気かい!」といって、必ず次に「最近、いいことあるかい?」とぼくにいう。
いつもそういわれるけれども、ぼくにとってはむずかしい質問で、とてもこまってしまう。
ずっと前にぼくが「社長、こんにちは。」というと、「おいター坊、社長なんて呼ばないで、これからは『二郎ちゃん』て呼んでおくれ!」といわれた。ぼくはそれ以来、『二郎ちゃん』と呼ばせてもらっている。
ある日、おじいちゃんと『二郎ちゃん』が宝くじの話をしていた。
おじいちゃんが『二郎ちゃん』にいった。「宝くじっていうのは、なかなか当たらんもんだな。」
すると『二郎ちゃん』が「わしは、宝くじに当たったためしもなければ、買ったためしもないよ。」といった。
おじいちゃんは「そうか、それじゃあ、当たったためしはないわな。わっはっはー。」と大笑いしていた。
この二人の会話を聞いていると、本当におもしろい。
「なみさん、最近、耳がとおくなったんじゃないかい?」と『二郎ちゃん』がいうと、「えっ、いま、なんていった?」とおじいちゃんがいう。
それでも、おたがいが心を理解しあっているから、何十年も友達でいられるのだろう。
二人は『ライオンズクラブ』という、ボランティア団体で様々なボランティア活動をしている。
おじいちゃんは、いつも『ライオンズクラブ』のある日を楽しみにしているので、ぼくは聞いてみた事がある。
「おじいちゃん、いつも『ライオンズクラブ』といっているけれど、なにが楽しいの?」
すると、おじいちゃんは「『ライオンズクラブ』のいい所は、いろいろなお仕事をしている人たちとお話ができることや、みんなで力をあわせてボランティア活動をすることで、いろいろなお友達が増えることだよ。でも、なんといっても、奉仕で人に喜んでもらえるのはとてもうれしいことだな。」と満足な顔でいった。
「ター坊も大きくなったら、いろいろなボランティア活動をして人に喜んでもらえる人になるんだよ。ボランティアというのは、お金をもらわないで自分の体と心で奉仕することだから、とても素晴らしいことなんだよ!」
そう教えてくれたおじいちゃんはとてもかっこよく、そして大きく見えた。
『ライオンズクラブ』には、メンバーの家族を連れて参加のパーティがある。そのときにぼくが驚いたことは、自分の誕生日にプレゼントをもらう時など、うれしい事があったときには「うおー!」と、大きな声でライオンのように雄たけびを上げて、うれしさを表現するのがルールだと知ったときだ。
また、自己紹介をするときには自分の名前の前にライオンをつける。例えば、田中さんだったら「ライオン田中です。」という。
他のメンバーの名前を呼ぶときには、相手の名前の後ろにライオンをつけて、鈴木さんだったら「鈴木ライオン」と呼ぶのだ。
初めてそれらを見たときは、本当にびっくりしてしまった。
極めつけは、会の終わりに『ライオンズクラブ』の歌を、全員で手をつなぎ、輪になって手を上下に振りながら歌うことだ。
このような光景をはじめてみたときは、たいていの人はぶったまげる。
しかしこれが慣れてくると、非常に楽しみになってくるので不思議だ。
世の中には、いろいろな会があると思った。
そして、おじいちゃんと『二郎ちゃん』は今日もグラスをかかげあい、乾杯をしている。 |
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
お散歩から帰ると、『おはようこどもショー』をおじいちゃんの『あぐら』をかいた『ひざ』の上に座って見る。
ぼくのくせは、おじいちゃんの大きな親指のつめを、ぼくの親指でこすることだ。
こうやってテレビを見ている時の安心感といったら、ぼくにしか分からないだろう。
そうやっているうちに、ママの声がする。「ご飯の用意が出来ましたよ!」
パパもママもおじいちゃんもぼくも『タック』のおばちゃんも、みんな正座して「いただきます。」をする。
いつのまにか、おじいちゃんとパパは『あぐら』になっている。ぼくもまねしてみるけれど、うまく出来ないので、もとどうり正座の姿勢にもどる。
ぼくもいつか、大人になったら、あんなかっこいい『あぐら』をしてみたいと思う。
『タック』のおばちゃんは、そんなぼくを見ていつも笑っている。
『タック』のおばちゃんは、亡くなったおばあちゃんの妹で、ママといっしょにご飯を作ってくれたり、掃除や洗濯など、おじいちゃんの身の回りのこともしてくれている。
何でぼくが『タック』のおばちゃんと呼ぶかというと、おばちゃんは犬が大好きで、『タック』というスピッツを飼っているからだ。
いつの日か『タック』が行方不明になってしまったことがあって、何日もおうちに帰ってこなかったことがあった。
みんなでさがすと、魚屋の『ジロー』という犬と仲良くなっていて、おうちののきしたで、こどもを産んでいた。
おばちゃんは、その『タック』のこどもに『ルー』という名前をつけた。
ぼくのおうちのちかくには、『グランド』という駄菓子屋さんがあって、いつも『タック』のおばちゃんは、ぼくを連れて行ってくれる。
この前『ルー』もいっしょに連れて行ったら、キャンディーをくわえているのに気がつき、『タック』のおばちゃんは、お金を払って『ルー』にも買ってあげていた。
『ルー』は、ママの『タック』にも食べさせたかったのだろう。
ぼくたち人間も、犬も気持ちはいっしょだと思った。
夜になると『タック』のおばちゃんはお酒を飲み過ぎて、「バターン!」という音とともに玄関や廊下で倒れて寝込んでしまうことがある。
ぼくは本当に『タック』のおばちゃんが死んでしまったのではないかと思って、急いで助けを呼びに行くこともしばしばある。
「たいへんだー!『タック』のおばちゃんが倒れたー!」というぼくの声に驚いてパパとママがとんでくることは、しょっちゅうである。
しかし、そんな『タック』のおばちゃんに対して、おじいちゃんをはじめパパもママも本当に優しかった。
いつかママがぼくに教えてくれた話では、『タック』のおばちゃんは戦争でだんなさんと子供を亡くしてしまい、ひとりきりになってしまったところを、おじいちゃんがお手伝いをしてもらうように頼んで、おうちに来てもらったということだった。
だけど『タック』のおばちゃんは悲しい顔は見せないで、いつも明るく、みんなのお世話をしてくれる。
お酒を飲んでぶっ倒れた次の朝、ぼくは心配で『タック』のおばちゃんの部屋に行った。
「おばちゃん、きのうは大丈夫だった?」と聞くとぼくの心配をよそに『タック』のおばちゃんは「何が大丈夫なんだい?きのう何かあったのかい?」といって何も無かったかのようにケロッとしている。
その言葉を聞いてぼくは内心ホッとする。
今日も『タック』のおばちゃんは、いつもと変わらない優しさで、ぼくと『タック』そして『ルー』を見守ってくれている。 |
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
ぼくの名前は、たかし。
おじいちゃんをはじめ、パパもママもみんな、ぼくのことを『ター坊』と呼ぶ。
おじいちゃんは、パパのお父さんで、ビールがとても大好きなので、『ビールじーじ』と呼ばれている。
『ビールじーじ』という名前をつけたのは、ママのお母さんで、ぼくのおばあちゃんだ。ぼくにはパパのほうのおじいちゃんと、ママのほうのおじいちゃんが二人いるから、分かりやすくするために『ビールじーじ』と名づけたのだと思う。
ここでは、パパのほうのおじいちゃん『ビールじーじ』について、お話をしていく。
ぼくは、生まれたときから、おじいちゃんといっしょにくらしている。
朝、ぼくは目がさめると、お布団をぬけだし、おじいちゃんの部屋にまっしぐらに行く。なぜかというと、おじいちゃんに、一番はじめに「おはようございます。」というのが、ぼくの一日の始まりだからだ。
ぼくがおじいちゃんの部屋に行き、お布団の中にいる、おじいちゃんの枕もとで「おはようございます。」というと、まってましたとばかりの、世界一優しい笑顔で「おはよう!」とぼくにいってくれる。
ぼくは、おじいちゃんのその笑顔と声が、何よりも大好きだ。
「ター坊、用意はいいかい?」、おじいちゃんがぼくに聞く。
「ぼくは、準備万端だよ!」と答え、いつものように、二人だけの散歩に出かける。
朝早くの散歩は、空気がおいしいし、朝日が町並みを、とてもきれいにうつしだしている。散歩の時、一番最初に行くのは『伝通院さん』というお寺だ。
ここには、ぼくのパパのお母さん、ぼくのおばあちゃんのお墓があって、おじいちゃんは毎日、ぼくが生まれた年に亡くなった、おばあちゃんのお墓にお水をあげてから、手のひらをあわせて、いろいろな出来事や、お話したいことを心で伝えている。
「ター坊、おじいちゃんが死んだら、お水じゃなく『ビール』をお墓にかけておくれよ!」とおじいちゃんはいった。
ぼくは、世界一大好きなおじいちゃんが死ぬなんていうことは、ぜったいに考えたくなかったし、そんな言葉が、おじいちゃん本人の口から出たことに、とてもショックをうけた。
「おじいちゃんは、絶対に死なないから、だいじょうぶだよ。ぼくがずっとそばにいて、おじいちゃんを守るからね!」
ぼくがそういうと、いつもの優しい笑顔で「ター坊、ありがとう!」といってくれた。
それから、ぼくらは小石川の『伝通院さん』から千鳥が淵まで歩いた。ちょっと疲れたけれども、その疲れも満開の桜を見た瞬間、とんでいった。
「ここの桜が、おじいちゃんは一番好きだな!お堀と桜の見事な景色だろう!」
そういったおじいちゃんの表情は、ぼくにきれいと感じることや、美しいと思える心を大切にしてほしいと、言っているように思えた。 |
|
 |
 |
 |
 |
|
